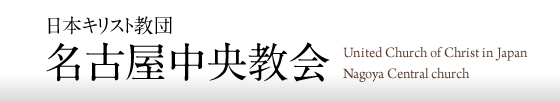「キリストの体として、一つにされる」 コリントの信徒への手紙一12章12~26節
以前、わたしが大阪の教会にいた時の事です。ある日、70代の女性がお二人、教会を訪ねてこられました。電車で4駅ほど離れた所にある、福音教会のメンバーでした。
お二人が所属している福音教会は、教団は違っていても、同じ地域にある教会として牧師同士、色々な場面で交流の機会がありました。とても紳士的な方で、また様々な問題にも積極的に関わる方でした。ある化学工場が汚染水を海に垂れ流ししている問題で、その従業員から相談を受けた時にも、地元の教会の牧師として協力してくださった方でした。精力的に牧師としての仕事をこなされる方でしたが、とても穏やかな方でした。わたしの尊敬するお一人でした。
ところが二人の女性が話されたのは、とても悲しい内容でした。お二人は、その教会のためにと献身的に奉仕してこられたのだそうです。日曜日だけでなく、平日にも教会に赴いては様々な働きを担ってこられました。ところがその牧師から、若い人たちを育てるため、その二人がしてきた奉仕をこれからはしないようにと求められたというのです。
お二人は「私たちは、あの教会にはもう必要ないんです」と、涙を流しながら語られます。「これまで、心を込めて奉仕してきたのに、来なくていいと言われたんです」と、心にたまった思いのたけを語り尽くされたあげく、「私たちの育てられた信仰は、こちらの教会とはだいぶ違っていますので、ここに教会籍を移すことは考えていませんが、しばらくの間、礼拝に出席させてください」ということでした。
お二人の話を聞きながら、人に事柄を伝えるのは難しいなぁ、と考えていました。その牧師の人柄を考えると、もう来るなと言われたとは考えられません。二人の女性を排除されるつもりで言われたのではないであろうことが想像できました。
ただ教会全体が活動的で、また若者も多く出入りしている教会でしたから、牧師のひと言でお二人は居場所を見失ってしまったのだろうと思います。お二人は、1ヶ月ほどで、別の福音教会へ移っていかれました。
教会には、様々な人が集まってきます。一人ひとりが神様の導きを求めて、信仰生活を送っている、そのことだけに焦点をあてれば、神社・仏閣を思い思いに参拝する人たちの如く、互いに干渉せず、自分の信仰を育むことだけを考えていればいいということになるのかもしれません。
しかし、パウロのコリントの信徒へ書き送った手紙には、様々な違った個性、特徴を持った者同士が、手や足、目や口、鼻や耳といった身体の各部分のごとき存在として、一つにつながっているのだと言うのです。
ユダヤ人とギリシア人、奴隷と自由の身分な者、価値観も生活習慣も全く違う者同士、共に交流するには、相当の覚悟で互いに配慮し合わなければ、一つの体の如き、調和のとれた、すべてが有機的につながっているような働きを持つことなどということは不可能です。
事実、コリントの信徒たちの間には、グループに分かれて、対立が深刻な状態にあったようなのです。
教会がキリストの体で、各部分が全く違った役割を果たすとしても、それが全体として一つの体の動きとして統一されているという譬えは、とてもイメージしやすい。
しかし、コリントの信徒たちの交わりの実際が分裂と対立を孕んでいたように、一つの体のイメージにふさわしいものとなるというのは、とても困難です。どうすればよいのでしょうか?
今日、読みました中に、3箇所、神について言及している部分があります。
13節「つまり、一つの霊によって、わたしたちは、ユダヤ人であろうとギリシア 人であろうと、奴隷であろうと自由の身分の者であろうと、皆一つの体と なるために洗礼を受け、皆一つの霊をのませてもらったのです。」
18節「そこで神は、ご自分の望みのままに、身体に一つ一つの部分を置かれたの です。」
24節「見栄えのよい部分には、そうする必要はありません。神は、見劣りのする 部分をいっそう引き立たせて、体を組み立てられました。」
いま、まずはこの24節に注目したいと思います。というのも25節につながっているからです。「それで、体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮しあっています、」と。各部分が互いに配慮し合い、分裂が起こらないのは、見劣りのする部分をいっそう引き立たせて、神が体を組み立てられたからだというのです。
見劣りのする部分を引き立たせられる。言い換えれば、弱さを中心において、体を組み立てられた。ここに神のみ心がある。
私たちは、強さを求める傾向があります。一人でもちゃんとやっていけるということが賞賛される。ところが神が中心に置こうとされるのは、強さではなくて、弱さです。いったい弱さには、どのような価値があるというのでしょうか。
私たちは弱ってしまった時、誰かの助けを必要とします。誰かの支えを求めます。私たちの力が衰え、そんなに早く仕事がこなせなくなってしまった時、誰かの手助けが必要となります。
弱さは、誰かの支え、配慮を必要とします。弱さは、私たちが1人で生きられないということを忘れないために、なくてはならないものです。
強さは、1人で生きる方向へ向かう可能性をもっていますが、弱さは、1人では生きることはできない、共に生きる方向へと向かいます。神は見劣りのする部分をいっそう引き立たせて、体を組みたてられました。交わりの中で、いつも弱さを中心において共同体を形づくることが、神のみ心なのです。そうすることで、体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮しあうのです。
そういう意味では、冒頭に紹介した2人の女性が通っていた教会は、とても大切な存在を失ってしまったということになります。どのような活動、働きを担う場合においても、弱さを持った人たちと共にあること、その弱さを中心に置く工夫、それが神様が求めておられることなのです。
さて、18節です。神は御自身の望みのままに、体に一つ一つの部分をおかれたのです。手や足、口や耳、目や鼻を体に置かれたように、教会という交わりの中に違った存在を置かれたのです。
私たちは、1人ひとり違った生活習慣を持ち、違った経験を経てきた者同士です。横におられる方をちょっと見てください。今、座っておられるところの隣の方です。お互いに見てください。軽く会釈してもらってもいいです。握手してもらってもいいです。気恥ずかしいかもしれませんが。礼拝の時は、前ばかり見ているので、隣の方に視線を向けることがあまりありません。今、確認したお隣と、自分とは多くの違いを持っています。
ところが、私たちは違いを多く抱えた者同士であることを忘れて、同じであることを求める傾向があります。同じ趣味の者同士が集まれば、話が弾みます。同じ考え方を持っている者同士で語り合っていれば、安心できます。共通理解を持っている者同士であれば、細かな説明などしなくとも話が展開していきます。細かな配慮をしなくとも、あうんの呼吸でやっていけます。
今お隣同士、違いを多く持っていますが、礼拝が進んでいく中で、私たちは同じ讃美歌を歌い、同じ交読文を読んでいる内に、違った者同士であることを忘れてしまいます。お隣が初めて礼拝に参加し、礼拝の進み具合について行けず戸惑いを感じておられたとしても、当然一緒に礼拝の展開についていけているものと思い込んでしまいます。そして、配慮を忘れてしまう。交読分を当たり前に、すぐ開くとができると思ってしまう。特にお隣同士、初めてお会いする方であれば、大丈夫かなと配慮することは必要となってきます。その配慮が共に生きる共同体として歩んでいく時、とても大切です。
また大阪での話になりますが、その地域ではアフガニサタン難民の家族を迎えその家族を支える市民運動に参加していました。
4人の子どもが通うことになった小学校で、4人にとっては初めての登校日、校長先生は朝礼で4人の子どもを全校生徒に紹介したのですが、アンニョン ハシムニカと始められ、しばらくハングルで4人を紹介しつづけられました。子どもたちは、きょとんとしています。
しばらくして、校長先生は、わたしの言ったことがわかりましたか、と子どもたちに尋ねました。「そんなん、わからへん」と子どもたち。校長先生は「わたしは、今、韓国・朝鮮の言葉ハングルで話しました。殆どの人が分からなかったかもしれません.今から紹介する4人の友だちは、まだ日本語が分かりません。だから皆さんが、わぁっと話しかけると、4人はびっくりするばかりです。そのことを配慮して、友だちになってください。」
こうして、子どもたちは学校へ通うことになりました。アフガニスタン人ですから、イスラム教徒です。宗教上、食べてはならないものがあるため、給食での配慮がなされました。女の子はある年齢に達すると肌をさらしてはなりません。制服のスカートははくことができません。これについてもズボンをはくことが認められました。
しかし、この家族の支える会のメンバーの中にも、こんなことを言う人もいました。「日本で生活することになったんやから、もう少し日本の生活の仕方を受け入れんといかんやろう。」違いを尊重し、受け入れるのではなく、同じようになることを求める傾向が私たちには強くあるのだということを痛感させられました。どうしても変えることはできない大切なものを誰もが持っています。それが、多くの人と異なるとしても、それを尊重することが求められているのです。
神はご自分の望みのままに違いを持った一つ一つの部分を共同体の中に置かれたのです。同じようになることを求める人の集合体の中で、同じになれず違ったままの存在としてキリストは、たとえ十字架に掛けられようと、この神の御心に歩まれました。そして、十字架に磔にされる犯罪者たちとさえ、その命の最後まで共にい続けられました。ここに神の愛が示されています。その愛を注がれて、私たちは生きているのです。
13節、わたしたちは、ユダヤ人であろうとギリシア人もであろうと、奴隷であろうと自由の身分の者であろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊をのませてもらっらのです。
私たちはどんなに違っていても、この神の霊によって生かされているという一点において一つとされているのです。
私たちは、同じになろうとする傾向の強い者であることを自覚することが必要です。その私たちを神は違いを大切にするよう導き、期待しておられるのです。
また、わたしたちは強さを求める傾向を強く持っている者であることを自覚しておく必要があります。その私たちに、むしろ弱さを中心にして共同体を形づくるよう導いておられるのです。
わたしたちが一つの体となるように、神の霊がこのように導いてくださっている、そのことに感謝し、委ねる者でありたいと願います。