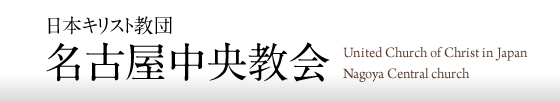「差別の現実の中、共に生きる」 ルカによる福音書15章1~7節
今日、私たちは部落解放祈りの日の礼拝として守っています。差別の問題を自分の問題として受け止め、自分自身を見つめ直すということがいかに困難であるか。今日の聖書を読むとそのことを痛感させられます。
ファリサイ派の人々や律法学者たちがイエスを非難します。「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と。イエスを非難している人々は、聖書ではイエスの敵対者として登場しますから、私たちは否定的な印象をもって見てしまいますが、当時の社会ではもっとも信頼されていた人々です。
神から祝福された生き方をするための道標である律法。これを日常の生活の中でどのように活かしていけばいいのか、そのことを絶えず考え実践していた人々です。正しく生きることを何より大切にしていた人々です。
律法学者たちは、宗教上の規約、清めに関する問題に決定を下す権威を持ち、裁判所の一員としても、また個人としても、民事事件に関する判決を下すことができる者とみなされ、それ故に信頼される人物でした。
ファリサイ派の人々は、神殿の祭司たちの特権を保持しようとする人々に対峙し、民の宗教とするために律法によって生活全体を整えていくことを大切にしました。
その彼らがイエスを非難しました。「この人は罪人たちを迎えて、食事まで一緒にしている」と。神の前に正しく生きようと、生活を律している立場からすると、とても受け入れられない者とイエスが一緒にいる。
しかも、彼らにとって食事というのは単なる食を楽しむことではなく、神から与えられた恵みに感謝し神を礼拝しつつ行われる神聖なものでした。その食事に罪人たちが同席することをイエスが許しているということが、彼らには受け入れられなかったのです。
イエスが話されたたとえ、1匹と99匹の羊の話はわたしたちも印象深く親しんでいるものです。羊はとてもデリケートな生き物だそうです。1匹だけで孤立すると、そのストレスだけで相当のダメージを受けてしまうということです。99匹で集団でいれば、羊飼いがそばにしばらくいなくても安全です。羊飼いは99匹を置いて、見失った1匹を探しに出かけます。道に迷い、パニックになって怪我をしていないか。野獣に襲われいないか。探し出すまで、気が気でありません。
そうしてやっと見つけた時、羊飼いの喜びは何にもかえがたいものであります。それと同様の喜びが、ここにあるのだとイエスは語られるのです。
このたとえ話の締め括りに、イエスは強烈な皮肉を語っておられます。「このように
、悔い改める1人の罪人については、悔い改める必要のないい99人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある」。つまり、あなたがた悔い改める必要がないと自負しているファリサイ派の人々や律法学者たちより、悔い改めなければ一緒に食事などできないと言ってあなたがたが排除している人たちのほうを神はずっと喜んでおられる、と。
その皮肉の鉾先は、ファリサイ派の人々の排除の心に向けられています。あなたがは悔い改める必要がないと自負しているのだろう、とのイエスの厳しい問いかけが聞こえてくるようです。
人は律法学者たちのように、誰かを排除する時、それなりのもっともらしい根拠を持っています。しかし、そもそも人を排除することなど神の御心ではないとイエスは言っておられるようです。
律法学者たちやファリサイ派の人々は、このイエスの声に応えて反省してはいません。むしろ頑なに心を閉ざし、イエスに対して敵意を膨らませていくことになります。
差別の問題を自分の問題として受け止めることを困難にする頑なさが、私たちの中にもあります。わたしたちは、イエスによっていつも厳しく問われなければ気づけない存在です。そして、喜びがどこにあるのかをイエスは明確に示されます。
部落差別を受け止めることを困難にしているのが、「今でも部落差別はあるのか」という疑問です。
つい先日、7月10日に名古屋市公会堂を会場に「部落解放をめざす愛知研修会」なる集会が開かれました。そこでの講演のテーマがまさに「今でも、部落差別はあるんですか?」でした。近畿大学の人権問題研究所の教授をしておられる奥田均先生から貴重な講演を聴くことができました。その一部を紹介します。
実は、部落差別はあるのかという問いは古くから問われてきていました。1965年に出された内閣同和対策審議会答申では次のように述べられています。
「世間の一部の人々は、同和問題は過去の問題であって、今日の民主化、近代化が進んだわが国においてはもはや問題は存在しないと考えている。けれども、この問題の存在は、主観をこえた客観的事実に基づくものである。」
この提言は、50年近くたった今も新鮮な響きをもって通用します。主観的には部落差別などないと感じていたとしても、それがそのまま客観的事実だと考えることは、まるで今も天動説に立って考えるのと同じような間違いに陥ることなります。私たちが日常感じているのは、朝になると太陽が東の空から昇り、夕方になると西の空に沈んでいくというように、空を太陽や月や星が動いているということです。つまり、主観的には天動説です。しかし、客観的には地球が宇宙を動いているのであって、地動説が正しいのです。
体験的には部落差別があるように感じられないから、もうないんだと判断することは天動説で見ているのと同じ事だと指摘されました。
奥田先生が教える学生たちは、全国から集まってきます。関東から入学してきた学生は人権教育を受けていないため、部落差別というと過去の身分制度くらいにしか考えていない。それで差別の実態について講義することから始められたそうです。
ところが大阪での差別の実態を例にあげ紹介して講義したところ、 学生たちは未知との遭遇のような反応。
学生に今日の講義は難しかったかと聞くと、先生大阪にはまだそんな部落差別があるんですね、という。君どこから来たんや、と聞くと福岡県行橋市というので、いやいや、あるかないかという議論やから具体的な例を示さないかんということで大阪の例を出しただけ、君の住む福岡県にも部落差別の現実があるんやで、と次の講義では福岡県の資料を配って講義したそうです。福岡の学生は良く分かりましたと、お礼を言いに来た。けれども教室全体はまだ未知との遭遇のような空気。また別の学生に今日の講義はどやったと聞くと、先生、大阪や福岡は大変ですね、そんな差別があって。君、どこの出身やと聞くと、高知やと言います。それで、高知の実態の資料を揃えて準備しかけて、途中でこんなことの繰り返しやと気がつかれました。1年かけて日本全国の差別の実態あれこれと講義することになってしまうと。それで方針を変えられました。
夏休みの宿題としてレポートするようにと課題を出されたのです。部落差別の現実について調べて9月に提出するようにと。
差別の問題について、先生から学ぶことしかしてこなかった学生たちはとても戸惑い、質問してきました。
わたしの住んでる町には被差別部落がないんですけど、そんな場合は何を調べてレポートすればいいでしょうか?
また別の学生は、中学の時、私の住んでる町にも部落差別があると人権の時間に教わったが、何町の何番地にあるということまでは教えてもらえなかった。先生は専門家やから知ってはりますよね。ぼくの住んでる町のどこが同和地区ですか?
少し要領のいい学生は、部落のことを書いたどんな本を元にレポートを作るといいですかとの質問。
これらに対して先生は次のように回答されました。自分の住んでる町に同和地区があるかどうか、そんなことは気にしなくていい。あったとして、どこが同和地区かということを知る必要もない。部落のことを書いた本を一冊も読む必要もない。その代わり、夏休みの間に自分の周囲の人と部落差別の問題について議論してほしい。家族でも、おじさん、あばさんでも、あるいは近所の人、クラスの友だち、アルバイト先の人でもいい。部落差別の問題についてどう思っているか、どう考えているか。率直なところ、話しを聞いてきて欲しい。その話の結果をレポートし、自分の感想を書き記すようにと。
さて、9月にレポートが集まってきました。
あるレポート。
「大学の近くの喫茶店で友だちとお茶してました。その時、宿題のこと思いだしたので、友だちに同和問題のこと知ってるやろ、お前どう思う宿題に出てんねん、と質問しました。すると、前の席でお茶しとった友だちが、急にびっくりしたような顔して、『何を急にそんな話し出すねん。こんなとこで、そんな話、そんな大きな声で。そんな話すんな。間違われたらどないすんねん。』と話を押さえにかかったのです。この学生は、部落差別はあるとは考えていた。けれど、それは17、18の若い世代の話ではなくて、年寄りの大人たちが性懲りもなく持っている古い考え方やと思っていたので、友だちの反応の意味が分からなかったんですね。何故、こんなところで、そんな話、そんな大きな声で、と友だちは言った。けど、こんなとこって、喫茶店。急に大きな声出してと言うけど、自分としてはさっきまでと同じ声のトーンで話していただけ。間違われたらどないすんねん、と友だちが言ったので、それどういうことやと質問し直したら、おまえそんなことも分からんのか。こんないろんな人がいるところで、同和とか部落とか言うてたら、あの子ら部落出身の子違うか、判断されたらどうすんねん。もし知っている人がいて、一回レッテル貼られたら、損することあっても得することない。一回レッテル貼られたら、そのレッテル剥がしようがない。おまえ、ええ年してそんなことも分からんのか、言われた。喫茶店で話題にすることすら憚られる、これは差別ではないですか。間違われたらどないすんねんと言った、現に部落の人たちが不利益を被っているということをみんなが知っているということ、これが差別の顕れですね、これが差別の現実ですね。」とレポートを書いていたということです。
もうひとりは、実家に帰ったある日、夕飯の片付けをしている母親の後ろ姿を見ながら、宿題を思いだしました。「お母さん、同和問題についてどう思う、と尋ねたのです。するとお母さんが、洗い物をしていた手をピタッと止めて、パッと振り返り、あんたなんでそんなこと聞くの、と真顔で問い返した。大学行って、人権論いう授業受けて、奥田先生から出た宿題やと言いました。すると、あんた大学行って、そんな勉強してんの、そんな講義そこそこにしときや、がんばらんでええでと言われたんですね。なんでお母さん、そんな言い方すんの、と問い返すと、なんでもええ、あんたかて社会出たら分かるようになると、ピシャッと会話を閉じてしまった。その学生は、わたしは今まで学校の勉強そこそこでいいとか、勉強がんばらんでいいとか言われたことがない。そんなふうに母親から言われたんは、これが初めて、と言います。部落問題はあんまり関わらんほうがいい、熱心に取り組まない方がいい、そんな取り扱いをされていること自体、差別ではないでしょうか。もしこれが、国際情勢についてとか、日本国憲法についてとか、日本経済についてとかやったら、あんたしっかり勉強しいや、と言われたであろうに、部落問題が別の扱いを受けている。これが部落差別だと思いました」という報告です。
夏休み前に、部落差別の実態について調べるようにと指示した時、学生たちの視線は同和地区につまり被別部落に向かった。ところが学生たちのレポートは、部落の外にある、部落出身者の登場しない部落差別の実態だった。
ごく普通の家の中で起こっている部落差別の現実、町の喫茶店で起こっている部落差別の現実を、学生たちが発見してきた。こんなレポートがあってな、と学生たちに紹介すると、それやったら分かると別の学生が、アルバイト先で、おまえそんなこと首突っ込むなよ、と諭されたと報告しました。
どうでしょうか。学生たち同様、これだったら私たちの周囲でも体験することと言えるのではないでしょうか。そして、これは教会においても同様です。ある教会の信徒の方が、今年の初め一階の私の部屋に突然来られました。その方は息子さんが大阪の大学に入学され下宿を探していたそうです。家賃の安い所を見つけたので近くの不動産屋に行った。ところが家賃の安い物件のことを頼むと、その不動産屋の担当者があの地域は良くないから止めた方がいいと言う。理由を聞くと、はっきりと言わず、他の学生さんたちもあの地域は避けはりますよ、と。
息子さんから相談を受けて、息子さんの希望された場所に行ってみると、隣保館があり人権を大切にしようという看板も立っている。これは部落差別やと直感して、こんなことおかしいとご自分の通っておられる教会で話題にだしたら、よう分からん言われたり、あんたあんまり深入りせんときや言われたり。
息子が差別に巻き込まれるような立場に置かれて、腹が立って仕方がなくて、この教会を紹介されましたと言って来られました。
私は、この方を部落解放同盟愛知県連までお連れして話をし、今は大阪府連で直接対応してもらっているところです。
主イエスは、全世界に出て行って、神の福音を述べ伝えなさいと言われました。しかし、部落差別の現実に触れないで避けて通る時、この主イエスの命令に背を向けることになります。全ての人に与えられた神からの喜ばしい報せを、わたしたちは文字通りに全世界にもたらすために、足もとにある部落差別の問題を克服しなければなりません。
そのためのモデルをイエスが与えてくださっています。差別の現実の中、排除されている人たちと共に生きることこそ、その第一歩ですし、神は最も喜んでくださるのです。