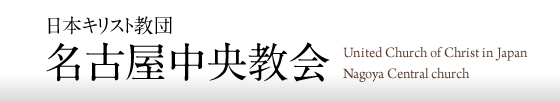「子どものように神の国を受け入れる」 マルコによる福音書10章13~16節
私が学生時代に出席していた教会は、大阪では割合大きな商店街の一角にありました。アーケードがいくつも枝分かれして続く商店街なのですが、教会が立っていた場所は住宅が十数軒並んでいる場所で、その一角だけアーケードが途切れています。そういう場所ですから、商店街で流れる音楽などの放送も礼拝中に聞こえてきます。
とてもリズミカルな音楽が流れている時、説教を聞きながらも、何人かの身体が音楽のリズムに合わせて小さく揺れていることがあります。いろんな景品の当たる抽選会の時は、「あめでとうございます。***町の****さん、1等賞です」とのアナウンスが聞こえてきます。知っている人が当たったのか、親子で遠慮がちに顔を見合わせ、小さく手を叩いていることもありました。
礼拝中なのに不謹慎なという批判もありますが、私には何かとても素朴な微笑ましい風景にうつりました。
今読みました聖書に「イエスに触れていただくために、人々が子どもたちを連れてきた」と書かれていますが、これもまた、ごく自然な微笑ましい風景のように思えます。多くの病人を癒し、打ちひしがれた人々に希望と生きる力をもたらされたイエスに子どもが健やかに成長できるよう祈ってもらい、祝福してもらえたらと願うのは、子どもを大切に思う親ならば当然のことです。
ところが弟子たちは、この人たちを叱りました。なんと非常識なことをするのかと厳しく非難したのです。子どもを連れてきた親たちは、場をわきまえない非常識な行動をしたと見られたのです。
弟子たちの非難に対して、私たちは違和感をいだきます。しかし、聖書のこの時代は、それは非常識なことだったのです。場をわきまえ、常識をわきまえ振る舞うこと、そのことだけを取り上げて考えれば、わたしたちもこれは当然のことと考えます。実は、この常識をわきまえるということが、時にくせ者となるのです。
たとえば、この礼拝に赤ん坊を連れた方が出席されていたとして、その赤ん坊がぐずり始めたとします。その親が、赤ん坊をなだめ、優しく揺すりながらも、なお礼拝堂に留まっておられるとしたら、皆さんはどんな風に思われるでしょうか。人それぞれ違うでありましょう。全く意に介さないという方。「うるさいなぁ。ぐずってる時くらい、外で過ごしたらいいのに。非常識やなぁ」と非難の視線を向けてしまう方。
さっき、私は、常識をわきまえるということが、時にくせものになると言いました。常識をわきまえる弟子たちは、子どもを連れてきた親たちを常識をわきまえないといって非難しました。
非難された親たちは、この時、どのように感じたでしょうか。子どもをイエス様に祝福してほしいと、とても素朴な率直な思いでやってきたはずです。そのイエスへの積極的な思いを遮られたのですから、どんなに寂しかったことでしょうか。さらに非難されたことで、自分を責める思いにまで至ったかもしれません。とにかく常識をわきまえていなかったのですから。
同様に、ぐずる赤ん坊をなだめながら礼拝に出席している人に、常識をわきまえていないといってつい投げかけてしまう視線は、その親に孤立感を抱かせ自分たち親子は、この神様に歓迎されていないと感じさせるかも知れません。
八木重吉が「神を呼ぼう」という詩を残しています。
「 さて、あかんぼは、なぜに、あんあんあんあん泣くんだろうか
ほんとに、うるせいよ、あんあんあんあん
あんあんあんあん、うるさかないよ、うるさかないよ
よんでるんだよ、かみさまをよんでるんだよ
みんなもよびな、あんなにしつこくよびな 」
赤ん坊のそのままを、神様を呼んでいる姿として受け止め直しています。あんあん泣いている赤ん坊に向かって「ほんとに、うるせいよ」としか感じ取れない人に、八木は「みんなも神さまを、この赤ん坊のように呼びなよ、あんなにしつこく」と呼びかけるのです。
さて、イエスはどうされたか。イエスは弟子たちの振る舞いを見て憤り、イエスの前で両手を広げて子どもたちを遮る弟子たちの手を振り払われました。そして子どもたち1人ひとりを抱き上げて、手を置いて祝福されました。子どもたちにとっても、子どもたちを連れてきた親たちにとっても、なんと暖かな光景でしょうか。
それにしても、弟子たちは、常識にとらわれ、その結果、この祝福に満たされた時間を遮ろうとしていたのです。しかも、彼らは、すでに子どもたちの命がどれほど重いものであるかを、イエスから聞いたばかりであったにもかかわらずなのです。
マルコ福音書9章36節にこうあります。
「そして1人の子どもの手を取って彼らの真中に立たせ、抱き上げて言われた。『わ たしの名のためにこのような子どもの1人を受け入れる者は、わたしを受け入れ るのである。』」
誰が一番偉いかを議論している弟子たちの愚かさを指摘する中でこのように語られたのです。イエスは、子どもの命の重さは、イエス自身の命の重さと同じであると語りかけられたばかりでした。
それなのに、今また、常識にとらわれ、子どもの命を軽視してしまいました。私たちも、日常生活の中でつい常識にとらわれ、神から示された命の祝福の喜びから離れてしまいます。礼拝においてさえ、ぐずる赤ん坊の声に「うるせいよ」と冷たい反応をしてしまうのです。
イエスは言われました。子どものように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることができない。「子どものように」とは、どういうことを指して言っているのか、色々な受け止め方ができます。しかし、これまでの文章の流れで見ると、当時の常識の中では、その存在がとても軽く見られていた、その「子どものように」神の国を受け入れる人でなければと読むことができます。
幼子の時、当然のことながら学歴も地位も何もありません。社会のために何か貢献するというわけでもありません。成長するに従って、家事の一端を手伝えるようになり、時には働き、役に立つようになります。学校に通えば、成績を気にし、良い点がとれれば評価もあがる。やがて充実した仕事をこなせば、重要な責任も担うようになり、社会的に重視されるようになる。
私たちは、幼い時には持っていなかった色々なものを、成長するにした従って身にまとってしまっています。そして、神さまに命を支えられているということと並んで、これら身にまとったものが大切で手放せなくなっていきます。
神さまが見守ってくださっているということ以上に、周りの人からどのように評価されるのかのほうが大切になってしまっているかもしれません。
たとえば道端にひっそり咲く花が炎天下でしおれてしまい、それが気になったとします。周りの人の「さぁ、先を急ぎましょう」という声に促されて、通り過ぎてしまう。そのようにして、私たちは、大切な命を1つひとつ後まわしにしながら、常識の落とし穴にはまってしまっているのではないでしょうか。
この世界が後まわしにしようとする命を、神さまはなによりも優先して見守っておられる。この世界がその存在にすら気づかないでいる悩み苦しむ命を、神さまは抱き上げ支えてくださる。
福音書の描くイエス・キリストがこのような神の愛を顕しておられます。幼い時から成長するに従って身に着けてきた、人から評価されるという事に心が奪われ、命の支えにしている限り、私たちは小さな命を後まわしに、無視しているのです。
身に着けた諸々の一切を脱ぎ捨て、幼子のように神さまに支えられて生きることにこそ喜びを見いだすことができるようになる時、私たちは最も小さな命にも心を向けることができます。人からどう見られるかにとらわれず、共に命を分かち合う者となる時、最も小さな命にも心を向け、共に命をわかち合う者となることができるのです。
しかし、弟子たちの如くなんども知らされながら、私たちも同じ誤りを繰り返します。この私たちを神が繰り返し正してくださるように、そして小さな命の重さをうけとめる者となることができるように、導きを祈り求めたいと思います。そして、赤ん坊のあんあんと泣く声と一緒に、神さまをあんなにしつこく呼ぶ者になりたいと願います。