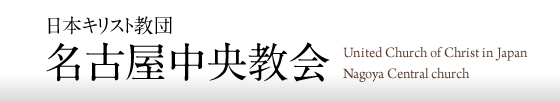「神の言葉は、すべての人に」 使徒言行録13章44~52節
私は、神学部を出て最初の赴任地での3年目に大変大きな水害を経験しました。教会のすぐ裏に川が流れていまして、普段は手長エビや鮎のとれるとても綺麗な川でした。子どもたちにとっては、格好の遊び場の1つでした。ところが、1983年の夏、長雨でこの川が氾濫し、広範囲にわたって町が水に浸かってしまいました。
この水害で破壊された町の復興のために、多くの工事関係者が来られました。復興工事が始まり何ヶ月か経った頃から、この町ではいやな噂が流れました。工事関係者が町に入ってきたことで、治安が悪くなったとか。どこそこで窃盗事件があった、犯人は工事関係者らしいだとか。子どもを早く家に帰すようにしないと危ないだとか。町の工事関係者に対する警戒心が強まりました。そんな噂が流れるようになり、私はとても悲しくなりました。
この町から20㎞ほど山に入ったところに1つの集落がありましたが、そこでは全く違った雰囲気が町を覆っていました。そこでは、復興工事の始まる初日、地元の小学校で工事関係の方々と町の人たち、子どもたちが集まって交流会がもたれました。 小学生たちに、学校の先生が工事関係者を紹介し、これから私たちのために工事をしてくれる方たちです、感謝しましょうと挨拶が交わされたのです。そんな風にして工事が始まりましたから、子どもたちは登下校のたびに、工事のおじさん、あばさんに挨拶します。なんとも暖かな人と人との交流がもたらされたのです。小学校の校庭での交流会はとても大きな意味がありました。
私たちは、限定された関係の中で生きていると、新しい出会いに対して心を閉ざす傾向があるのです。
さて、今日読んだ聖書の箇所は「次の安息日になると」という言葉で始まります。つまり、前の安息日にあった出来事を受けて、今日のところの展開があるのです。ここでいう安息日というのは、金曜日の日没から土曜日の日没までで神を礼拝する日のことです。前の安息日、パウロとバルナバはピシディア州のアンティオキアという町にある会堂に入って席についていました。
会堂というのは、ユダヤ教徒たちが共に集い、聖書(旧約の律法と預言書)を学び、神を礼拝する場所です。ユダヤ人とユダヤ教に改宗した外国人から求められて、パウロはイスラエルの歴史を振り返り、そしてイエス・キリストについて語りました。使徒言行録13章38~39節。
「イエス・キリストによる罪の赦しが告げ知らされ、またあなたがたがモーセの律 法では義とされ得なかったのに、信じる者は皆、イエス・キリストによって義と されるのです。」
つまり、律法に記されている掟の1つひとつを守り、神の前に正しく生きることで、神さまから祝福される者となることは、ついになかった。わたしたちは不完全で、罪深い。たとえ自分を律して清く正しく生きているつもりでいる者であっても、その結果、いいかげんな生き方をしている者を見るとさばき、見下げる黒い心が現れる。
しかし、そんな私たちをイエス・キリストは導き、そのままの私たちで神が受け入れてくださるように整えてくださった。このイエス・キリストの導きを信じ、その導きに従って生きる者は神の恵みに満たされ生きることができる。このようにパウロは語ったのです。
この話を聞いたユダヤ人たち、また改宗してユダヤ教徒になった者たちも感激し、次の安息日にも、その話を聞かせて欲しいと頼んだのです。
そうやって迎えた次の安息日というのが、今日のところです。ところが、今日、ユダヤ人たちの態度は一変しました。パウロの話しに感激し、その話しをもう一度聞きたいと言っていたユダヤ人たちが、口汚くののしって、パウロの話すことに反対したのです。
理由は、町中の人がほとんど集まってきたからです。ユダヤ人と改宗してユダヤ教徒になった人たちだけはなく、その他の諸々の人々が集まってきた、その群衆を見て、ユダヤ人たちは妬んだというのです。
このユダヤ人たちの妬みとは何なのでしょうか。これを知る手がかりは、このあとのパウロとバルナバの言葉にあります。46節。
「そこでパウロとバルナバは勇敢に語った。『神の言葉は、まずあなたがたに語られるはずでした。だがあなたがたはそれを拒み、自分自身を永遠の命を得るに値しない者にしている。見なさい、わたしたちは異邦人の方に行く。』」
ユダヤ人たちは、ここに異邦人が一緒にいるということが許せなかった、受け入れられなかったのです。ここでパウロに反対しているユダヤ教徒たちは、旧約の長い伝統を背景にして、ユダヤ人こそ世界の諸々の民族の中心に立つことのできる存在である、との誇りを抱いていました。そして異邦人と交流すること、一緒に食事することも禁じ、閉じられた集団として様々な地域の中でも、独自のコミュニティーを形作っていました。
神の導きの歴史を語り、神の特別な導き、救いを語るパウロたちの大切なメッセージを分かち合う場所に、ユダヤ教の信者以外の者、すなわち異邦人が入りこんできたことが受け入れられなかったのです。
私たちは、限定された関係の中で生きていると新しい出会いに対して心を閉ざす傾向があります。
しかし、パウロが前の安息日に、すでにユダヤ人以外の人々にも開かれた神の導きを語っていたのです。信じる者は皆、イエス・キリストによって義とされる、神に受け入れられると語っていました。我々はモーセの律法では義とされ得なかった、旧約の伝統に立つだけでは神に受け入れられる者となることはできなかった、と語っていました。
パウロに反対するユダヤ人たちは、多くの異邦人が押し寄せてきたことで、ユダヤ人以外の人々にも開かれた神の導きをパウロがすでに語っていたことに初めて気づいたのかもしれません。ユダヤ人たちは、口汚くののしって、パウロの話すことに反対したのです。パウロの語る神からのメッセージを受け入れようとしないユダヤ人たちを前に、パウロとバルナバは「あなたがたは、神が示してくださった素晴らしい永遠の命を得るには値しない。わたしたちは、あなたがたが拒否する異邦人の方に行く」と宣言しました。
そして、さらに重要なことを言います。あなたがたは、異邦人を拒絶する。しかし、旧約の古の預言者がすでに異邦人にも神の恵みは開かれていると語っているではないかと。
「わたしは、あなたを異邦人の光と定めた。あなたが、地の果てにまでも、救いを もたらす。」
とイザヤ書49章に記された預言を引用して示すのです。ところで異邦人たちはユダヤ人たちのパウロを口汚くののしり、その語ることに反対する声に、心を痛めていたのではないでしょうか。パウロを罵る声は、そのまま異邦人たちを否定する内容を持っていました。ですから、イザヤ書を引用し異邦人たちの方に行くと言ったパウロの言葉にどれほど励まされたでしょうか。パウロの語る言葉を聞いて異邦人たちは喜び、神を賛美しました。
そして、永遠の命を得るように定められた人は皆、信仰に入りました。この定められている人という表現は、信仰に入る人と入れない人とが予め定められているという意味ではありません。信仰への歩みは、神さまの導きによるのであって、パウロたちの働きがもたらすものではないということを表現しているにすぎません。
とにかく、パウロたちが呼びかけた言葉に、異邦人たちが応答し、神の言葉が、その地方全体に広がり、その地方の人々の心に刻まれることとなったのです。
しかし、パウロたちを口汚くののしり、その語ることに反対したユダヤ人たちはおさまりません。神をあがめる、つまりユダヤ教の教えと伝統に共感している貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害し、その地方から2人を追い出してしまったのです。
閉じられた関係の中に異質な存在が入ることを快く思わず、これを排除しようとする傾向が私たちの中にはあります。冒頭で紹介したこともそうですが、今、日本にも多くの外国人が生活するようになり、これを快く思わず、排除しようとうするいやな空気が広がるっていることはご存知だと思います。
外国人が増えたことで、治安が悪くなったとか、犯罪発生率が増えたなどということがまことしやかに、国会議員までが口にすることがあります。
しかし、事実は全く異なります。これは、ある人権問題に関する集会で資料を用いて紹介されたことです。警察が発表する「犯罪白書」によれば、外国人の人口増加の著しさに比較して、外国人の犯罪は減少傾向にあるということです。これは今でも、インターネットで犯罪白書を調べることで確認できます。
外国人が著しく増えているが、外国人による犯罪は減少傾向にある。この事実に反して、外国人が増えたから、治安が悪くなったという嘘がまことしやかに、人々の口にのぼるのです。経済格差が広がり、全体的に生活し辛くなっていることが人々を暗くしてしまっているのでしょうか。
パウロとバルナバを迫害したユダヤ人たちのように、異質な存在に対する暴力は今も昔も変わりありません。日本の大阪や東京の在日韓国人朝鮮人が多く生活しておられる地域で、くり広げられるヘイト・クライム、ヘイトスピーチで、「良い韓国人も、悪い韓国人も殺せ」などという言葉の暴力を大音量であびせる行為が続いています。
在特会という右翼団体の暴力行為は、ついには日本基督教団など多くのキリスト教団体の事務所が入っていた東京早稲田にあるキリスト教会館に対しても行われました。今は、この建物は耐震工事が必要であるということで、各事務所が別に移転していますが。
使徒言行録は、聖霊、つまり神の霊がキリストの弟子たちを導いて、イエス・キリストのもたらされた素晴らしいメッセージ、福音を世界のすべての人々に述べ伝えていく様子が描かれたものです。そして、13章からは、パウロを中心にその教えを述べ伝える宣教の様子が記されています。
その赴いた先々で、パウロたちは迫害に遭います。命の危険にさらされることも度々です。ユダヤ人の暴力に対して、パウロはどのように対応したのか。51節に記されています。かつてイエス・キリストが弟子たちに指示されたように、福音が受け入れられず、追い出されるような時、足の裏の塵を払い落として、町を去るようにしたのです。そのような迫害の中で、無理をすることはしなかったということです。
「私たちは異邦人の方にいく」と宣言したパウロたちですが、14章を見ると、次に立ち寄った町でもユダヤ教徒の礼拝する会堂に向かい、ユダヤ人とギリシア人に語りかけているのです。
こうして、イエス・キリストの福音は多くの困難にも関わらず、世界に広められたいきました。そのすべては聖霊による導きに支えられたものであったと、使徒言行録は描いています。
そして、その行程の中で、閉ざされた同質なものの関係の中に閉じこもろうとする私たちの傾向を、神さまは突き破って異質なものに出会わされ、私たちの命をより広がりのある豊かなものとしてくださる導きがあることを感謝したいと思います。そして同時に、私たちの中にうごめく、同質なもので固まろうとする、その関係の中に安住しようとする罪を自覚し、この私たちを打ち砕き、新しい出会いへと導いてくださる神さまに委ねる者でありたいと思います。そこに福音は、より豊に輝くのです。