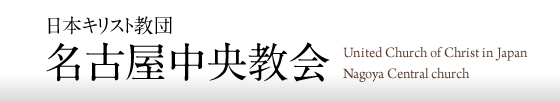「天の国はその人たちのもの」 マタイによる福音書5章1~12節
わたしたちは、意味ある人生を送りたいと願っています。長く生きれば、生きるほど、悩みを抱えてることもあり、後悔を引きずっていることも多々あります。それでも、生きていて良かったと思える人生を送りたいと願います。
しかし、あまりにも悲惨な経験をすると、生きていてなんになるのかという、追い詰められた気持ちになってしまいます。これまでにも紹介したことがありますので、あ~、あの人のことね、と思いだされる方もおられると思いますが、石川正一さんという23歳で生涯を閉じられた方がおられます。
この方は筋ジストロフィー(進行性筋萎縮症)という病気でした。筋肉に栄養がゆきわたらないためにおこる病気で、足から次第に痩せ衰えてゆき、やがて全身の筋肉が萎縮し身動きできなくなってしまいます。心臓も筋肉ですから、やがては死を迎えることとなります。1955年生まれですから、もうすでに故人となっておられます。筋ジストロフィーにもいくつかの種類があるそうですが、石川さんの場合、15歳から20歳までの間に死を迎えるということでした。
最初に気づいたのは、幼稚園の頃です。様子が変だと言うことで病院へ行ったところが、この病気を知ります。9歳の頃の、お母さんの手記です。
「今日、弟の雄二のお友だち4,5人が家へやってきて、正一も一緒になって遊んでいました。そのうち子どもの1人が『テレビの漫画が今から始まるよ』と言いだし、雄二も一緒になって外に出て行ってしまいました。むろん正一は、必死になってそんな子どもたちに、置き去りにされまいと引きとめていたのでした。
結局、みんなが行ってしまった後の寂しさに堪えられなくなり、
「ぼくなんか生まれてこなければよかったんだ」と大きな声で叫んだのです。
正一がそんな言葉を口にしたのは最初のことです。
誰にあたることも出来ず、洋間の床の上をゴロゴロところがり、じゅうたんをもみくちゃにしながら、泣きはらした顔を見たときには、さすがにわたしも胸がつまりました。信仰のたらないわたしのこと、とっさになだめすかす術もわからず、子どもと一緒に泣き崩れてしまいました。」(石川正一『たとえぼくに明日はなくとも』立風書房38頁)
この時のことを振り返り、石川正一さん自身も詩に書き残しておられます。
「お母さん
もう一度立ってみる
ちきしょう
ちきしょう
ぼくはもう駄目なんだ
ぼくなんかどうして生まれてきたんだ!
生まれてこなければよかったんだ!」
それでも気を取り直し、いろいろなチャレンジをしながら成長していく正一さんは、中学生になって、父親に自分の病気につてい尋ねます。この時のことも詩に残しておられます。
「お父さんね
自分の病気を
自分が何もしらないということは
いけないことだと思うよ
だから全部教えて
こわいから言うんじゃないよ
こうき心で聞くんじゃないよ
生きるということは
自分をしることなんだよ」
そして、お父さんから20歳までしか生きられないことを知らされます。あと数年しか生きられないと知って、お父さんとの語り合いの後に、そうであるなら、完全燃焼すべく励もうと奮起します。しかし、そんな自分の中にうごめく妬みや怠慢の罪に気づき、完全燃焼しきれない自分に生きる意味を見いだせなくなってしまいます。
わたしたちは、たとえ順風満帆な人生を歩んでいたとしても、突然の事故や自然災害で、その全てが崩壊するかもしれない、実は不安定な命を生きています。そんなわたしたちは、意味ある人生を送りたいという願いをどのように満たすことができるのでしょうか。
そんな問いを持つわたしたちにとって、今日の聖書のイエスの語られる幸いな人たちというのは、その冒頭から意外すぎます。「心の貧しい人々は、幸いである。天の国はその人のものである。」
ここで心と訳されている言葉は、霊、息、命とも訳されるプニューマというギリシア語です。心、霊、息、命、それらの意味を合わせ持つプニューマ、それが貧しい人。どのような人を連想することができるでしょうか。
自分を誇りうる何ものをも見いだせない人。自分で自分を信頼できない人。自分の生きている価値を見いだせない人。
例えば幼い頃から、厳しすぎる親の非難の声を浴びながら成長した人は、自信が持てず、自分は価値がないとさえ思われ、追い詰められてしまいます。
あるいは、大変な暴力にさらされ、瀕死の重症をおいながらも生き延びて回復することができた人が、それでも暴力で圧倒され、自分の命の尊厳を粉々に砕かれ、心に深い傷を負ってしまうことがあります。このような人も、自分の価値を見いだせず苦しむこととなります。
また、病気や事故で動けなくなった人も、自分の価値を感じ取ることができず苦しみます。石川正一さんもその1人でした。
そのような人が、どうして幸いだと言えるのでしょうか。天の国はその人たちのものだからだというのです。死んだ後で天国に迎えられます、などという意味ではありません。聖書の世界では、天というのは神のおられるところとして思い描かれています。そうすると、天の国といのは、神さまと共にいることと言いかえることができます。
聖書の最初、創世記1章には神さまがこの世界を造られた様子が描かれています。最初、世界は混沌としていて、闇が覆い、水で満たされていました。そこに光をもたらし、水を大空の上と下に分けることで命の宿る空間を造り、大地をもたらし、種を持つ草と、実をつける木を生えさせられます。大空には、季節と時のしるしとなる星々、月、太陽を配置されます。
このようにして、命あるものが宿る世界をもたらされ、その創造の業を成し遂げられるたびに、1つひとつこれを良しとされ、喜ばれます。
やがて、海の魚、空の鳥、そして大地を駆ける獣、地を這う生き物をもたらされます。そして、最後に人間が神に似せて造られたとあります。最後に人間が造られたことについて、奥田知志という北九州でホームレス支援をしている牧師が大変興味深い解説をしています。
「人類が登場する前に、太陽ができたり、月ができたり、大地ができたり、草ができたり、魚ができたり、動物ができたり、いろいろなものを神さまは創っていきます。そして、最後に人類が登場します。その理由は、人は、他のものが全部そろっていないと生きていけない存在だったからだと思うのです。他のものが全部そろって初めて生きていける、それが人なのです。
その手前にいろいろ整っていないと人類は生きていけない。つまり、人類はそれほど弱い存在であるということです。」
こうして最も弱い存在である人間をも配置されたすべてのものをご覧になって、神さまは、それらは極めて良かったと見られたと記されています。神さまは、この命豊かに宿る世界を心から喜ばれ、慈しまれたということです。神さまは、この世界を、そこに生きる命ある者を愛するために創造されたのです。神さまは、この世界をそして命あるものを必要とされているのです。
その世界で最も弱い存在である人間を、神さまはご自分に似せて創られ、最も必要とされているのだと、創世記が描きます。
心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。
自分を誇りうる何ものをも見いだせない人、自分で自分を信頼できない人、自分に生きている価値を見いだせない人。そのような人と、神は共にいることを選ばれる。神はそのような人を必要としているのだと、イエスは語られるのです。
このイエスの言葉は、宣言であり、約束です。自分で自分の必要性を見いだせない人に向けて、神はあなたを必要としておられ、あなたと共におられるようになるのだ、天の国はその人たちのものである、とイエスは祝福の宣言をされるのです。
天の国はその人たちのものであるとの宣言をされる人々が10節にも登場します。義のために迫害される人々です。義というのは、神との本来あるべき関係に生きるという意味です。時代の流れに呑み込まれず、神さまが本来わたしたちに望んでおられる生き方を求めて歩むことです。
このような生き方のために迫害される人々の事について、さらに説明が加わります。11節、わたし(イエス)のためにののしられ、迫害され、云々と続きます。迫害される者は、義のため、そしてイエスのためと並べられています。ここから、義とはイエスのことと読むことが出来ます。主イエス・キリストにおいてこそ、神との本来あるべき関係に生きる者の姿が示されているのです。
天の国はその人たちのものである、という3節と10節にはさまれるような形で、「幸いである」という人々の事が記されています。このような形式で書くことで、天の国に生きる者の、つまり神が共にいることを望まれる人々、神が必要とされている人々の更に細かな内容を4~9節で描いていると言えます。
今、その1つ1つを細かく見ることはしませんが、主イエスが、このようなメッセージを語られたきっかけのほうに目を向けたいと思います。5章1節。
イエスは、この群衆を見て、山に登られ、そして、弟子たちを近くに寄せて語り始められた、とあります。この群衆とは、5章の直前に記されています。4章23節~25節(23節~25節を朗読)。
病気に苦しみ悩む者、悪霊に取り憑かれた者、てんかんの者、中風の者、
一般的には、人々から遠ざけられ、社会の周辺に追いやられていた人々です。人々から、やがて忘れ去れていく存在でした。
誰からも必要とされていない空しさと、やるせなさを味わいながら、病気に伴う辛さに堪えて生きなければならない人々でした。なぜこんなに苦しみながら生き続けなければならないかと、嘆く者もいたでありましょう。
ただ、そのような病人たちだけではありませんでした。そのような病人をイエスのもとに連れてきた人たちもいました。社会の多くの人々が敬遠する病人たちに敢えて近付き、寄り添い、イエスのところへ伴ってくる人々が存在したのです。
このような群衆がイエスに従ってきたのを見て、イエスは山へ登られ、そして語り始められたのです。このような人たちを神は必要とされている、神はこのような人たちと共にいることを選ばれるのだと言われるのです。
わたしたちは、意味ある人生を送りたいと願っています。その願いに促されて、わたしたちは意味ある存在になろうと努力し、人々から必要とされることで喜びを見いだそうとします。それ自体、積極的な意味を持っています。それが励みとなり、生き甲斐となります。
しかし、すべてがうまくいくわけではありません。そもそもがわたしたちは弱い存在なのです。この世界のすべてがそろった最後に登場したのが人間です。すべてのものが整っていないと生きることのできない弱さを持っているのが人間です。
しかし、神さまは、そのような人間を必要とされているのです。「心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。」
主イエスは、弱さを抱える者に神さまが与えられる祝福を共に分かちあう生涯を歩まれました。時の指導者からどんなに妨害されることがあっても、社会の周辺においやられた者と共に生き続けられました。
「義のために迫害される人々は、幸いである。天の国はその人たちのものである。」
わたしたちは、自分の中に意味がみいだせなくなってしまうような辛さをかかえている時にも、神さまが必要とされているのだというところから歩み出す者でありたいと願います。
意味ある人生、それは今のままのわたしたちを、神さまが必要とされているということに支えられているのです。石川正一さんは次第に動けなくなっていく中で、生きる意味を求めて、模索し続けられ、その辿られた心の軌跡をノートに記録しつづけられました。やがては自らペンを握る力もなくなり、正一さんが口で話されることを、母親がノートに書き取られるようになります。
その一部にこのように書かれています。
「神さまの台本に従うということは、成り行きにまかせに生きることではない。精一杯に生きる中から、台本の全容が次第に見えてくる。
死の受容とは諦めることではない。残り時間を大切に生きることで、よりよき死を迎えようとする、新たな生の歩みを意味する。
筋ジスの人生を、神さまから選ばれて与えられたと信じているからこそ、懸命に生きた結果を、神さまに委ねるという信仰が成立する。」(石川正一『めぐり逢うべき 誰かのために』立風書房253頁)
神さまが今のままのわたしたちを必要とされている。他の誰も期待しないとしても、自分ですら自分に期待できなくなってしまったとしても、神はわたしたちを必要とされ、わたしたちに歩むことを期待しておられるのです。
その神の見守り、期待に支えられ、今のままの自分から、自分なりのペースで歩んでいきたいと願います。
「心の貧しい人々は、幸いである。天の国はそのような人たちのものである」