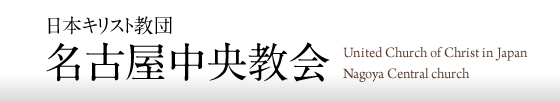「キリストの僕として」 ガラテヤの信徒への手紙1章1~10節
現在、牧師として働いている私の友人の1人は、かつて教会の中での人間関係のトラブルが原因で牧師を辞めた時期がありました。彼は、当時、教会を出て、引っ越し屋の仕事をしました。数年働いて、やがて再び牧師として働くことを志すようになったのですが、その時の思いを語ってくれたことがありました。
彼は、親の代からクリスチャンで、母親の胎にいる時から教会に通っていました。命の尊さ、生きる意味、それらは教会こそが人々に語ることができる。教会を通して、神の御心が人々に語り伝えられ、この社会がより良く変えられていく。そのように信じて、神学を学び、牧師の職に就くこととなりました。
ところが、彼が大切な生きる場所として考えていた教会の中での人間関係で傷つき、追われるようにして、喜びであったはずの牧師の職を辞することになったのです。
心に傷を負い、痛みを抱える彼を迎えた引っ越し屋の仕事仲間が、彼の慰めとなってくれました。仕事で出向いた先での引っ越しされる家庭の方々の何気ない日常の会話の中にも、素朴な温もりを感じ取った彼は、徐々に癒されていきます。仕事の不十分さを補い合う仲間たちにも励まされました。
そして、教会の中で学び、教会の中でしか知ることができないと思っていた、命の尊さ、生きる意味が、この日常の人と人とのふれ合いの中で豊に示されていることに気づかされたというのです。
神さまは、教会を通さずに直接この世界に働きかけ、導きを与えてくださっている。人々が行き詰まりを感じてしまうような場面にも、神さまの導きが隠されている事を、この日常の人と人との触れ合いの中で感じ取った彼は、その喜びを語りたいと渇望するようになりました。
人々は気づいていないようなところに、神さまの導きが隠されている。教会には、その現実を人々に伝え共有する大切な使命があると彼は考えるようになり、再び教会へ戻り牧師として働くようになったのです。
彼は、この体験を次のようにたとえて語ってくれました。神学部を卒業して、教会で働き始めた当初、自分は両手にいっぱい持っていた。それまで学んだきたこと、みんなに伝えたいことを、両手に抱えていた。やがて挫折を経験し、すべてを両手から手放すことになってしまった。
けれども、すべてを手放して気づいた事があった。自分の周りに神さまからの恵みがいっぱいあるということ。人と人との触れ合いの中に、共に働く中に、神さまの導きが隠されていることに気づかされた。
それまで自分は両手にいっぱい抱えていたため、神さまからの恵みを受け取るにも、手が空いていなかった。神さまからの導きを受け取るにも、両手がいっぱいで手を伸ばすゆとりがなかった。彼の経験した挫折は、本当の意味で神さまの導きに委ねるために必要なことだったというのです。
最初にこのことを紹介させていただいたのは、今日のガラテヤの信徒への手紙を読んでいて思いださせられたからです。
この手紙を書いているパウロも、深い挫折を経験した人でした。パウロは、ユダヤ人の民族的な誇りという点では、申し分のない人生を歩んできた人でした。神がユダヤ人の祖先に与えてくださった律法、これを学び実践する厳しい道を歩んでいました。当時のパウロにとっては、新しく興ってきたイエスをキリストと信じる者たちの、その信仰の内容は神を冒とくするものとしてしか受け止めることができませんでした。
その結果、ユダヤ人たちがステパノというすぐれたクリスチャンを捕らえられ、これを取り囲んでこぶし大の石で殺害した時、まだ若かったパウロはこのステパノを殺害する人々の上着を預かってそばにいたのです。
この時、ステパノはひたすら神を見上げているばかりでした。石で傷つけられ命を奪われていくままにまかせて「主よ、この罪を彼らに負わせないでください」と大声で叫び、息を引き取ったのです。ステパノの殺害に賛成していたパウロは、それから後もクリスチャンたちを脅迫し、殺そうと意気込んでいました。彼は、クリスチャンたちの苦痛の叫びと血をあびながら過ごしていたのです。
ある時、パウロはエルサレムへ連行するクリスチャンたちを捕らえるため、ダマスコという場所へ向かいます。ところがこの時、復活のイエスの「なぜわたしを迫害するのか」と問う声を聞くのです。
パウロはこの声を聞いて雷にうたれたようになり、ショックでしばらく目が見えなくなってしまいます。私は、このイエスの問いかけは、実はパウロ自身もひきずっていたことではないかと想像しています。
クリスチャンたちを捕らえ、殺害してきました。けれど、当のクリスチャンたちはステパノに見られるように、敵であるはずの自分たちのために神の祝福を祈る人々でした。
イエスが「敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい」と命じられたことがその支えでした。そこに真の命の道があることを信じて生きているのがクリスチャンだったのですが、そんな人々を捕らえ、殺害するパウロの心の底に「なぜ私はこの人たちを迫害しているのか」という疑問をひきずっていたのではないかと思います。
けれど、パウロは両手にユダヤ人としての誇りをいっぱい抱えていました。ダマスコ途上で、このパウロに「なぜ、わたしを迫害するのか」と抗いがたく響く声を聞き、頑なだったパウロの心は揺り動かされ、打ち砕かれてしまいます。
なぜわたしを迫害するのかとの問いかけは、パウロの心の底に引きずっていた自分自身の問いを呼び覚まします。「わたしはなぜこの人たちを迫害しているのか」。「わたしは、いったい何をしてきたのか」。衝撃のあまりパウロは三日三晩、何も食べることも飲むこともできないほどになってしまいます。
このパウロにイエスが新しい道を示されます。それは、パウロが否定して止まなかったイエス・キリストのことを語り伝える、伝道者の道を行くことでした。しかし、それはそれまでの仲間からは、裏切り者と見られ、命の危険を伴うことです。また、パウロを迎えるクリスチャンたちも、恐ろしい迫害者である彼を受け入れてくれるかどうかの保証はありません。
しかし敵を愛し、迫害する者のために祈るクリスチャンの1人として生きることに、パウロは自分の命の道を見いだしたのです。
この背景があるパウロですから、彼は手紙の冒頭で自分のことをここに書かれているような形で自己紹介できたのです。
「人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストと、キリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされた」パウロは、挫折を通してキリストの導きに委ねる者に変えられたのです。そして、イエス・キリストの導きに生かされる道に歩み始めたところから、かつてのユダヤ人としての誇りに生きていた自分を振り返って、いかにその誇りとしていたものが意味のないものであったかと言います。
フィリピ書3章5~8節でこう書いています。
「わたしは、生まれて8日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人です。律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした。しかし、わたしにとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに損失と見なすようになったのです。そればかりか、わたしの主キリスト・イエスを知るこのとあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失とみています。キリストのゆえに、わたしはすべてを失いましたが、それらを塵あくたと見なしています。」
パウロは、ユダヤ人の中でもエリートの1人としての誇りをもって生きていました。しかし、その誇りの故に、他を迫害し、深い挫折を経験することとなったのです。
イエス・キリストは神に支えられて生きることを徹底し、民族の誇りや、伝統の誇りなど人間の営みに絶対的価値を置いて生きることを一切拒否されました。
これを快く思わない者たちは、このイエス・キリストを十字架にかけて処刑してしまいました。イエス・キリストは十字架刑で、さらし者にされながら死んでいかれました。惨めさを背負い、すべての誇りから切り捨てられました。
しかし、このイエスがただ一点守っているものがありました。神に委ねるということです。すべてを失っても、神にすべてを委ねることのできる命の道をイエスはこのようにして切り拓かれたのです。イエス・キリストは、神にすべてを委ねつつ、十字架で処刑されましたが、神はこのイエスを復活の命へと導かれました。
神にすべてを委ねて生きる者を人がたとえ阻もうとしても、神は十字架をすら克服して命へと導いてくださるということが明らかにされました。
パウロは、このイエス・キリストに呼び出され、深い挫折の向こうに真の命への導きを知る者となったのです。
私たちが両手にいっぱい抱えているままでは、神から与えられる命への導きを受け取る手は空いていません。私たちの生きるこの世界には、人が手放せないと考える様々なもので溢れています。富や文明、社会的地位や学歴、国家主義や民族主義。
キリストは、この悪の世からわたしたちを救い出そうとして、ご自身を献げてくださったのです。キリストの十字架、そこに私たちの挫折が重なります。大切だと思ってきたすべてを失うところから、新しい命の道が開かれるのです。
私たちが洗礼を受けるというのは、この十字架、挫折の死に我が身を委ねるということです。そして、ただ神によって生きる命の道を改めて歩み始めることなのです。
しかし、洗礼を受け、イエスの挫折の死に与り、神によって生かされる新しい命に生きる者とされた時も、なおわたしたちは社会的地位や学歴、国家主義や民族主義といったものを誇りにするようにとの誘惑にかられます。そのような時、わたしたちは改めて両手に抱えているものをまず捨てて、神からの導きを受け取る原点に立ち返る者でありたいと願います。
わたしたちが、なんらかの挫折を経験する時、神さまによって生かされる大切な機会がもたらされているということを思い起こしたいと願います。わたしたちが両手に抱えている大切なものを失う時、改めて神さまに委ねて生きる道へと導かれているのです。